訪問介護事業所
誰が自宅に訪問してくれる?
訪問介護サービス利用を交わした事業所から、主に 下記資格のいずれか取得したホームヘルパーが訪問します。
・介護福祉士
・介護員養成研修修了者
・介護職員初任者研修修了者
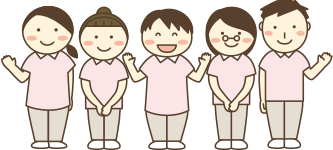
受けられるサービス内容
訪問介護で受けられるサービス内容は2種類あります。
身体介護サービス生活援助サービス
身体介護サービスの具体例
身体介護サービスとは、身体に直接ふれて行う介護のことをいいます。
- 食事介助
- 食事の際の支援
- 入浴介助
- 全身または部分浴
- (顔・髪・腕・足・陰部など部分的な洗浄)
- 清拭
- 入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること
- 排泄介助
- トイレの介助やおむつの交換など
- 歩行介助
- 自分の足で歩くことができるように介助すること
- 更衣介助
- 衣類の着脱など着替えの介助
- 体位変換
- ベッドの上など床ずれ予防のための姿勢交換
- 移乗介助
- ベッドから車いすに移す際の介助
また、定められた研修課程を修了するといった一定条件を訪問介護員が満たすことで、「たんの吸引」などを行うことが可能になりました。
生活援助サービスの具体例
生活援助サービスとは、生活に必要な家事が困難な場合に行う日常生活支援のことをいいます。
- 掃除
- 居間の掃除、ゴミ出しなど
- 洗濯
- 衣類を洗う、干す、たたむ、整理まで
- 食事準備
- 食材の買い物代行から、調理・配膳・片付けまで
- 移動介助
- 「起き上がる」「座る」「歩く」等の行為が困難な場合の介助
- 移動の際の介助
- 受診手続き
- 病院の付き添いや薬の受け取り代行など
- その他
- 爪切り・血圧測定・耳垢の除去など医療行為でないもの
訪問介護で受けられないサービス
訪問介護は、前提として要介護者の利用者本人だけを対象としたサービスです。
つまり、ご本人が日常生活を送るうえで関係のない行為や、医師や看護師など専門資格でなければできない医療行為等は訪問介護で受けることはできません。
訪問介護サービスでは受けられないもの
-
ホームヘルパーがやらなくても
生活に差し支えがないもの ・家具の移動や電気器具の修理
・床のワックスがけ・窓のガラス拭き
・家具の修理
・庭の草むしり
・ペットの散歩 など -
医療行為にあたるもの
・インスリンの注射
・経管栄養の交換
・点滴の交換、たんの吸引作業
・摘便や床ずれの処置 など -
本人以外の方に対する行為
・家族の分の食事を作る
・家族の部屋の掃除
・家族の衣類の洗濯などの家事代行
・家族の子供の面倒を見る など
料金について
介護保険の負担割合は、所得に応じて、1割・2割・3割のいずれかとなります。
介護サービスを利用するときは、介護保険負担割合証に記載されている利用者負担割合に応じて、サービス費用のうち1割から3割までのいずれかが利用者の負担となります。
ただし、給付額減額措置を受けている場合は、そちらが優先されます。
利用者負担割合は、65歳以上の方は1割、または一定以上の所得のある場合は2割、特に所得の高い場合は3割となります。
40歳〜64歳までの方は1割となります。
判定基準
3割負担となるのは?
1.65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額※1が 220万円以上
2.前年の合計所得金額※2と前年の年金収入の合計が
- 同一世帯の65歳以上の人数が
1人の場合
340万円以上 - 同一世帯の65歳以上の人数が
2人以上の場合
合計で463万円以上
※1合計所得金額から、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。
※2合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得金額及び土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。
2割負担となるのは?
1.65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額※1が 220万円以上
2.前年の合計所得金額※2と前年の年金収入の合計が
- 同一世帯の65歳以上の人数が
1人の場合
280万円以上340万円未満 - 同一世帯の65歳以上の人数が
2人以上の場合
合計346万円以上463万円未満の
両方にあてはまる方
または、
1.65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額※1が 160万円以上220万円未満
2.前年の合計所得金額※2と前年の年金収入の合計が
- 同一世帯の65歳以上の人数が
1人の場合
280万円以上 - 同一世帯の65歳以上の人数が
2人以上の場合
合計346万円以上の両方にあてはまる方
※1合計所得金額から、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。
※2合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得金額及び土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。
65歳未満のかた、市民税非課税の方、生活保護受給者は1割負担となります。
介護保険サービスを利用するときには、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証の2枚を一緒に介護保険サービス提供事業者にご提示ください。
在宅(自宅)でサービスを利用する場合
要介護度別に介護保険からの支給限度額が「単位」で決められており、その範囲内で利用した分のサービス費用の1割から3割までのいずれかが自己負担となります。
支給限度額を超えてサービスを利用することもできますが、その分は全額自己負担となります。
| 要介護度 | 改定前(単位) (令和元年9月まで) |
改定後(単位) (令和元年10月から) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5003 | 5032 |
| 要支援2 | 10,473 | 10,531 |
| 要介護1 | 16,692 | 16,765 |
| 要介護2 | 19,616 | 19,705 |
| 要介護3 | 26,931 | 27,048 |
| 要介護4 | 30,806 | 30,938 |
| 要介護5 | 36,065 | 36,217 |
※11単位は10円から10.7円となります。(サービスの種類ごとに異なります)
※2居住サービスのうち、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護(地域密着型含む)、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、支給限度基準額の対象となりません。